作家 伊集院 静さんの作品に「神様は風来坊」というエッセイ集があります。(もとは週刊文春の「二日酔い主義」というコーナーに連載された作品を文庫化したものです。)
そのなかに「バイオリンの音色」という小編が載っています。伊集院さんのお姉さんが高校受験に失敗した時のことが書いてあります。
文庫は絶版になっていますが、このまま埋もれさせるには惜しい作品なので、自分が持っている古本から文字起こししました。
悲喜こもごもの春に参考になる方もいるのではないでしょうか。
ななかまどの木が風に揺れていた。
実はまだ青く、葉はあざやかな緑に萌えていた。
「秋になったらまた来るといい。 この実が赤くなって綺麗だからよ」
新潟弁でキャディーさんが言った。
湯沢高原のゴルフ場にいた。
「そんなに急いでも同じだよ。 後ろの組もいないし、ゆっくり行こう。スイングもゆっくりだよ」
目元の愛らしいおばさんだった。前のホールでショートパットを外した私が、首をかしげてパターのスイングをしていると、そばで、「いい天気だ、今日は、ほれ、あの雲見ろ」と空を見上げて雲を指さしていた。 そのキャディーさんのペースで、半日ゆっくりゴルフが楽しめた。
どこにも達人はいるものである。
夕暮れ、越後湯沢駅のプラットホームで、電車を待って並んでいる五、六歳の女の子が三人いた。その女の子の一人が私の姪に似ていた。
すぐ上の姉の子で、私はこの姪を見るのが好きだ。
まだ彼女が三歳の頃、 田舎の実家 に遊びに来ていた。長姉と次姉の子供たちと居間で遊んでいた。父は五人の孫の遊び道具にいろんなものを買って来ていた。昔は子供たちが、夜店で何かを買って欲しいと言 ったら、すごい剣幕で怒っていた父が、孫には平気でいろんなものを買って来ていた。
そのひとつに雉の剥製があった(私は父のこういう趣味が信じられないのだが)。 東京で生まれ育った 五人の孫たちは、初めて見る尾の長い雉を囲んで顔を見合わせていた。
すぐ上の姉の子だけが、少し離れた場所で、柱に隠れるようにして考え込むような目で 雉を見つめていた。
他の孫たちは小学校に上っていたから、剥製の意味はわかっていた のだろう。一番腕白な長姉の子が、 雉の尾を手でさわった。すると遠くから父が、「さわっちゃいかん。その鳥は夜になると飛ぶんだから」 と言った。父はよくその手の冗談を言うことがある。
父の言葉に雉の周りの子供たちが笑った。
柱のそばの姪だけが、これ以上目が開かないというくらい目の玉をまんまるにして、雉と父を交互に見ていた。
翌朝、姪は赤い目をしていた。眠れなかったらしい。 私は姪の気持ちがよくわかる気がした。
「この子は将来性があるよ」
と私が言っても、姉は父のいたずらに怒って、娘を連れて早々に東京へと帰って行った。
その姪が先月、京都に遊びに来た。小学生になっていた。姉と印象派の絵画展を見学 に来たという。食事に連れて行く道すがら、姪は彼女が行きたい大学の話を私にしてく れた。私は驚いた。まだ小学一年生の女の子の口から、東京の私立大学の名前がすらすらと出た。
「なんだよ、この子はどうなってるんだ」
姉に聞くと 「もうこのくらいの年から、目的意識を持たせなきゃいけないのよ」
「それは違うだろう」
「いいのよ。 あなたは今の受験戦争がわかっていないのよ」 姉は私を睨むように言った。
三人の姉たちは大学に行かせてもらえなかった。父は姉たちが高校を出たら、働きに 出るか家の商売を手伝って、そのうちに結婚をさせようと考えていたらしい。
「高校までは出してやるから、あとは家の手伝いをしろ」
父は口癖のように言っていた。姉たちは中学生になると、洗濯屋の伝票整理をしたり、 ダンスホールの切符売場に座らされたりしていた。
「学校の成績が悪いようなら、すぐに学校をやめて、家の手伝いをしろ」
中学生の姉たちにむかってそう言っていた。そのせいか、姉たちは皆学校の成績が良かった。
だが、父は子供たちの成績を良くするために、そう言っていたのではなかった。その 証拠に我が家では高校の受験は、町で一番優秀な高校(こう書くと聞えはいいが、あの 頃私の町には四つの高校しかなかった)しか受けさせてもらえなかった。 今で言うスべリ 止めは一切受験をさせない。
「試験に落ちたら高校へ行くな。 すぐ家の手伝いをさせるから」
子供たちは皆必死だった。
姉の一人が高校の受験に失敗した。 父は怒り出し、姉の部屋からバイオリンをつかんで庭に叩き捨てた。怒りはおさまらなかったらしく、酒を飲み始めた。深夜、子供が全員起こされた。
皆酒臭い父の前に正座した。 落第した姉は父に殴られたらしく、頬を赤くして泣いていた。
「いいか、おまえたちもよく覚えておけ。この子は明日から家で働かせる。 試験に落ちるような奴は学校へは行かさない」
と朝方まで説教をした。姉を可哀相だと思った。
母の頬も赤くはれていた。 母が父に泣いて頼んで、姉は私立の高校へ再試験を受けて通い始めた。町では普通高校と私立高校では制服が違った。
「裏口から家を出ろ」
と世間体を気にする父は言った。姉は三年間じっとそんな声に耐えて学校へ通った。 私立高校を首席の成績で出て、卓球部では市で個人優勝する選手になっていた。姉の意地のようなものがそうさせたのかもわからない。私はそんな姉を見ていて、立派だと思った。
すぐ上の姉は学業成績が良かった。 家庭科コースなのに進学コースの生徒と並んでもトップクラスの成績だった。
或る日、担任の教師が家に訪ねて来て父に姉を大学に進学させてはどうか、奨学金の資格試験も姉なら受かる、と話した。
父はその話を聞いていて、
「先生、女が大学に行って何の役に立つんですか。第一学校に行けなくてちゃんとし た仕事をしている男の嫁に行けないでしょう。金はあるんだ、私の家は。 しかしそれはこの子たちが嫁に行く時に使う金だ。大学なんぞのためじゃない」
そう言って断った。
だが姉たちは、裁縫学校へ行かせましょうという母の絶妙な父への進言で、東京の服装学校へ行った。そうして見事にあの家を脱出した。
その姉たちが結婚して娘が生れると、驚くような教育ママになった。
義兄たちはそん姉の姿を見て、タメ息をついている。
その現状を父が見たら、父はどんな顔をするだろうか。
あの夜、庭に叩きつけられたバイオリンは、父の憤怒のあらわれなのだろうが、その 激情の底から低い音色でこのうえもなく姉をいつくしんでいた父の呟きが聞えるような気がする。
伊集院静 「神様は風来坊」文春文庫










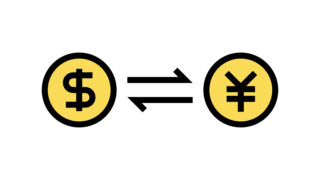











コメント